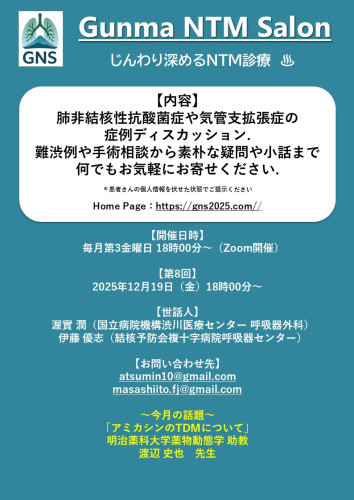お知らせ
ERJ openの論文です。
イタリアのStefanoのグループからの単施設の報告になります。
2021年7月から2024年12月の期間にIRCCS Humanitas Research Hospitalで登録された気管支拡張症574例のうち、139例(24.2%)で気管支鏡検査が行われていました。
この研究対象患者では、全例気管支洗浄が行われていたようです。
気管支鏡検査を行った所、58.3%で菌が検出され、菌種の内訳は以下の通りでした。
・H. influenzae:15.8%
・P. aeruginosa:15.1%
・MAC:11.6%
・S. aureus:6.5%
・A. fumigatus:4.3%
特に、喀痰が得られない、あるいは培養陰性が続く症例でも、菌の陽性率は60%以上と高率でした。
さらに、この結果、51.1%で治療の方針に変更があったようです。
気管支拡張症の患者さんに気管支洗浄を行う際には、検査後の増悪が懸念されますが、今回の研究では検査後の増悪に関する記載はありませんでした。
実臨床では、菌が未検出でも増悪を繰り返す症例や、胸部CT所見が悪化していく気管支拡張症を経験するかと思います。
そのような症例では、気管支鏡検査の検討が必要かもしれません。
難病情報センターから、「特定医療費(指定難病)受給者証 所持者数」の情報が公開されています。
特定医療費(指定難病)受給者証所持者数 – 難病情報センター
令和6年度末の時点では、群馬県では3名の患者さんが、線毛機能不全症候群の指定難病に登録されておりました。
線毛機能不全症候群は令和6年4月に指定難病に登録されました。
同年6月には、外注の遺伝子検査が保険適用となっています。
まだまだ線毛機能不全症候群の患者さんは、県内に多数いらっしゃるかと思います。
外注の遺伝子検査で診断がつかない場合には、専門施設へご紹介ください。
全国では74例の方が登録されております。
▶各県の登録人数
東京:18
埼玉:6
長崎:6
神奈川:5
石川:4
福岡:4
群馬:3
千葉:3
北海道:3
岡山:3
兵庫:3
広島:2
宮城:2
新潟:1
富山:1
三重:1
京都:1
大阪:1
和歌山:1
奈良:1
徳島:1
熊本:1
大分:1
鹿児島:1
沖縄:1
先日発出されました, ERSとATS合同のPCD診断ガイドラインについてまとめてみました.
■Introduction
●PCDの原因遺伝子>55遺伝子
●PCDの有病率:1/7,500 ←近親婚の頻度や民族の閉鎖性に影響を受ける.
●PCDの特徴:早期からの湿性咳嗽, 鼻副鼻腔炎, 内臓位置異常, 中耳炎, 不妊
●伝音難聴だけでなく, 感音難聴もきたす.
●男性不妊の原因:精子鞭毛もしくは精巣輸出管の線毛運動の障害.
●女性不妊の原因:卵管内の線毛運動の障害.
■PCDの確定診断
★遺伝子型と表現型の違いが予後に影響し, 将来的に遺伝子特異的治療の選択肢となり得るため, 可能な限り遺伝学的診断を強く推奨する.
■以下の場合は,「PCD highly likely」と診断する:
1) VUSが1アレルまたは2アレルに存在する場合, あるいは中等度のエビデンスを有する遺伝子に病的または病的と考えられるバリアントが認められる場合.
⇒TEM Class2, HSVM異常あり, IF異常ありのいずれかがあれば.
2) TEMでclass 2欠損がみられる患者
⇒遺伝子検査, HSVM異常あり, IF異常ありのいずれかがあれば.
3) TEMと遺伝子検査でも異常を認めなくても…
⇒典型的なPCDの臨床症状あり+nNO低値+HSVM(Post-cell culture)で異常あり
の場合.
★検査結果が不確かであったり, 一貫した結果が得られない場合には, 再検査を行う.
■PICO1: nNOでPCDを疑うべきか?
●1A:During velum closure (軟口蓋を閉鎖した状態)←レジスター法
推奨の強さ:Strong
エビデンスの確実性:moderate
統合感度は 93%(95%CI: 88–95%), 統合特異度は 88%(95%CI:79–93%)
●1B:During tidal breathing(安静時呼吸)
推奨の強さ:条件付き
エビデンスの確実性:very low
感度は 77%~100%, 特異度は 57%~90%
(対象研究数が少ないため統合解析は実施せず、3研究が含まれた)
■PICO2: HSVMでPCDを疑うべきか?
●2A:Post-cell culture
感度は 92.5%(95%CI: 70.9–98.4%), 特異度は 98.1%(95%CI: 91.2–99.6%)
●2B:Pre-cell culture
感度は 97.9%(95%CI: 93.7–99.3%), 特異度は 80.0%(95%CI: 54.7–93.0%)
推奨の強さ:Strong
エビデンスの確実性:very low
■IFでPCDを疑うべきか?
推奨の強さ:Strong
エビデンスの確実性:high
感度はそれぞれ 0.84-0.88, 特異度は 1.00
■PICO1-3のまとめ
●nNO, HSVM, IFは, PCDの検査としては有用であり, PCDの診断アルゴリズムに含めることができる.
●どの検査も感度や特異度は100%ではないため, 複数の検査を組み合わせるべき.
●特定の検査を特定の順序で実施すべきだという根拠は存在しない.
●遺伝子検査またはTEMにより診断が確定できない場合には, 追加検査を要する.
●全ての検査が常に必要となるわけではない.
●施行する検査を必要以上に限定した場合, 診断精度が低下する可能性がある.
●診断は, 可能な限り専門センターに紹介すべきである.
2025年8月12日に12歳以上の非嚢胞性線維症性気管支拡張症に対してFDAで承認されたBrinsupri®ですが, 11月18日にEUにおいても販売承認が正式に付与されています.
Brinsupri®以外にも複数のDPP-1阻害薬の開発が進んでいます.
今回は, Respiratory ResearchからPublishされたDPP-1阻害薬のmeta-analysisの論文を紹介します.
本論文は, HSK31358(SAVE-BE), BI1291583(AIRLEAF), Brensocatib(Willow study), Brensocatib(ASPEN study)の4つのRCTを統合したものになります.
●ベースラインのまとめ
・マクロライド使用率:5-19%
・ICS使用率:5-63%
・緑膿菌感染の頻度:33-36%
・年齢:56-64歳
・年3回以上の増悪歴あり:21-35%
・入院を要する増悪(24か月):24-37%
・喘息合併:7-20%
・COPD合併:9-27%
・BSI:7-9点
・%FEV1:67-74%
●有意差があった項目:
増悪回数, 重症増悪回数, 初回増悪までの期間, 喀痰中好中球エラスターゼの減少, 呼吸器症状の変化
●差がなかった項目:
%FEV1の変化、2回以上の増悪患者、3回以上の増悪患者、有害事象
個々のRCTでは%FEV1の低下を抑制する効果が報告されておりますが, meta-analysisでは有意差はなかったようです.